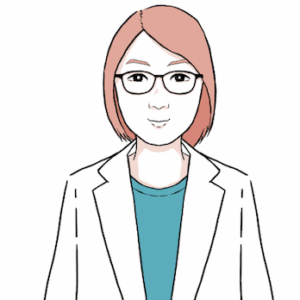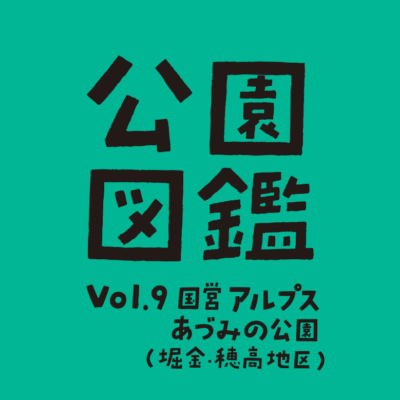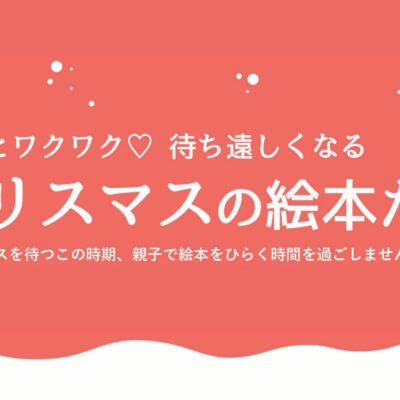【のびのびトイロ vol.6】子どもの忘れ物が多くて、 困っています。

多様な子育てを応援するアプリ「のびのびトイロ」では、子育て中のみなさんから寄せられた不安や悩みごとについて、信州大学医学部子どものこころ発達医学教室の先生方が中心にお答えするQ&Aコーナーを配信中です。その中から転載してご紹介します。
お悩み「子どもの忘れ物に対する対策って?」
子どもの忘れ物が多くて、困っています。学用品を忘れたり無くしたりすることが多く、文具などはいつも2セット用意しています。また、上着や帽子を身につけるのを忘れることもあります。朝、帽子をかぶるのを忘れたり、上着を羽織って出たのに学校に置いてきたり、手で持って帰ってきたり。小さなものから大きなものまで、なんでも忘れてしまうのですが、何か対策はありますか?
児童精神科医・牧田みずほ先生がアンサー
わざとではなく、本人も困っています。
誰にでも、忘れ物をすることはあります。うっかりミスをしたり、体調が悪くて普段通りにできなかったりと、原因はさまざまです。複数の要因が関わることもあります。人によって状況は異なりますが、どのお子さんも何度かは忘れ物を経験していることでしょう。
ただ、同じものを何度も繰り返し忘れてしまい、生活面で困ることが多いようであれば、なんらかの対策が必要です。そのような問題が続くと、まわりの人から注意される回数が増えて、本人が落ち込んでしまうこともあります。
忘れ物をした本人は、わざとやっているわけではありません。どうすればいいのかがわからず、一人で困っている場合が多いです。その気持ちに寄り添いながら話を聞き、忘れ物の要因を探ったり、忘れ物を防ぐ対策を一緒に考えたりしていきましょう。
忘れ物が多いとわかっているのなら、手伝ってかまいません。
子どもが一人で持ち物の用意ができるようになればいいのですが、精一杯努力してもミスが出てしまう子もいます。完璧を求めず、まわりの人がサポートをして、忘れ物をしにくい環境、忘れ物をしても困らない状況をつくっていきましょう。
小学生のうちは、本人が「自分は忘れっぽい」「こういうやり方がいい」などと自覚するのは難しいです。大人の側が「この子は忘れ物をしやすい」とわかっているのなら、手伝ってしまってかまいません。むしろ大人が手伝うことで、子どもは「人に相談したり、頼ったりすれば忘れ物は減らせる」ということを知ります。成功体験を通じて「なんとかなる」と思えるようになり、自信がついていくこともあります。
忘れ物をしにくい環境をつくっていきましょう。
対策として、次のような方法が考えられます。お子さんに合う方法を選んで、忘れ物をしにくい環境をつくっていきましょう。
- 子どもが必要な持ち物を把握できるように、持ち物リストをつくる。口頭で伝えるだけでなく、文字やイラストでわかりやすく示す。親や先生が一緒にチェックする。
- 朝は忙しいという場合には、前日に持ち物の用意をする時間をつくる。用意したものを置いておく場所も決めておけば、朝はそこにあるものを持っていくだけでいい。
- 子どもが片付けが苦手な場合には、よく使うものの置き場所を決めておく。イラストや写真を貼って「これはここに置く」と示すとわかりやすい。
- 親と先生で相談して、連絡事項をメモや付箋などの形でお互いに提供する。子どもだけに任せるのではなく、大人どうしも連絡をとり合うことで、子どもをサポートする。
- 子どもに「忘れ物をして困ったときには大人に相談する」と伝えておく。大人は相談を受けたら叱らないで、子どもが自分から相談できたことを肯定的にとらえる。
- 持ち物リストなどの利用に子どもが慣れてきたら、徐々に本人に任せるところを増やしていく。スモールステップで取り組む。
このような工夫によって、忘れ物をある程度は予防できるでしょう。しかし、それでも忘れ物をする日もあると思います。子ども本人もまわりの大人も、「忘れ物はする」という前提で行動しましょう。完璧を求めないようにしてください。
また、成功や失敗に一喜一憂しないことも大切です。失敗をいちいち叱っていたら、子どもの緊張感が高まります。また、成功したからといって大げさにほめると、子どもに「次もがんばって」というプレッシャーをかけてしまう場合もあります。ほめるとしても、うまくできて本人が喜んでいるときに「よかったね」と軽く声をかける程度で十分です。
ご相談には帽子や上着を忘れる、身につけずに帰ってくるというお話もありますが、この点には少し注意が必要です。子どもたちのなかには、感覚過敏があって帽子や上着などを身につけるのが苦手な子もいます。「親から言われたときには我慢して身につけるけれど、できればつけたくない」という子もいるのです。そのような特徴に心当たりがある場合には、医師などに相談して、対応を検討したほうがいいかもしれません。

信州大学医学部子どものこころの発達医学教室が開発した、「個性に合わせた多様な子育て」を応援するアプリ。周りの子と、自分の子を比べてしまって不安になる…。そんなときはこのアプリを開いて、子どものそれぞれの育ちについて学びましょう。AIチャット機能を新搭載!