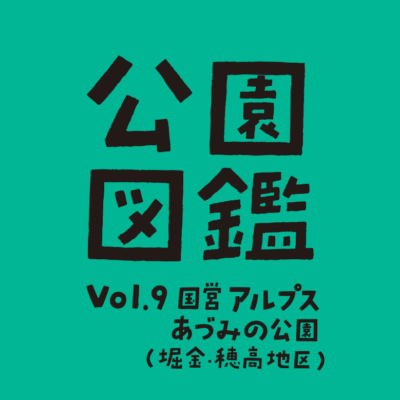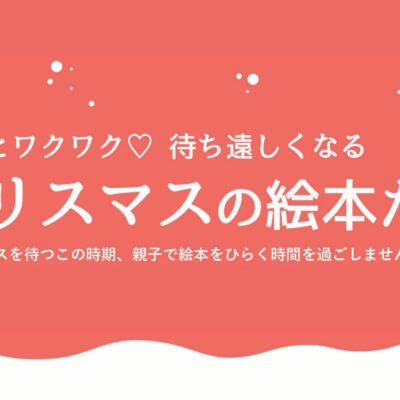【のびのびトイロvol.5】子どもが虫を殺して遊んでいて心配です。

多様な子育てを応援するアプリ「のびのびトイロ」では、子育て中のみなさんから寄せられた不安や悩みごとについて、信州大学医学部子どものこころ発達医学教室の先生方が中心にお答えするQ&Aコーナーを配信中です。その中から転載してご紹介します。
お悩み「子どもの虫の観察、どこまで許容するべき?」
子どもが虫に興味を持っています。公園などに行くと虫を捕まえるのですが、機械を分解するようなやり方で、虫を生きたまま引き裂いてしまうことがあります。虫の羽根や脚などをちぎって、観察しています。生き物の体がどうなっているのかを知りたいのだと思いますが、残酷で見ていられません。「かわいそうだから、やめようよ」と言っても、やめてくれません。どうすればいいのでしょう?
児童精神科医・篠山大明先生がアンサー
多くの子がそういう経験をするものです。
子どもが公園などで虫を殺して遊んでいると、親としては残酷な行為だと感じることもあると思います。ただ、多くの場合、小学校低学年くらいまでの子どもにはしばしばそのような行為が見られます。ほとんどの子どもが、そういう経験をするものです。「子どもが虫を殺す」という行為自体は異常なことではないので、安心してください。
そのような行為をする理由としては、「興味がある」「遊んでいる」「虫が嫌い」「ストレス発散になる」といったことが考えられます。小学校低学年くらいの時期に興味本位で虫遊びをしているというのは、不健全な行為ではないと思います。
虫遊びの経験は、生き物の生死の理解につながることもあります。一つの成長過程としてとらえましょう。なかには「ものを壊す」といった不適切な遊びに発展する場合もありますが、虫遊びをしている子がみんな、そのような経過をたどるわけではありません。親としては「やがてもっと残酷な遊びをするのでは」と不安になるかもしれませんが、あまり先回りせず、不適切なことがあればそのつど対応していくということで、十分だと思います。
何を伝えるかを考える機会にしましょう。
虫などの生き物を殺す行為自体は異常ではないということをふまえて、対応法を考えていきましょう。虫遊びは多くの子がすることですから、やめさせるというよりも、そのような行為を通じて何を伝えるかを考える機会にしてはどうでしょうか。子どもはみんな、周囲のさまざまな刺激にふれながら成長していきます。虫遊びを通して学べることもあります。
例えば、虫などの生き物を扱うときの、最低限のルールを教えるのもいいでしょう。具体的な例をあげながら、「みんなが嫌がるときには虫遊びをしない」「危険な生き物にはさわらない」といったことを伝えてみてはどうでしょうか。
ただし、あまり細かく指摘すると、重要なことが伝わりにくくなる場合もあります。親の側が「これだけはわかってほしい」ということを絞り込んで説明し、大きな問題がない行為は見守るというのもいいと思います。
説明する際に、法律や宗教などを例として示すのもいいかもしれません。例えば虫は動物愛護法の対象ではなく、他人の所有物でもないので、おそらく法的な問題はありません。一方で、法律で保護されている生き物もいます。子どもの年齢によっては、そのような説明をしてもいいと思います。また、家庭に宗教的な背景があり、一切の殺生を禁じる考えがあるのなら、それを伝えるのもいいでしょう。特にそういった背景がなくても、一般的な常識として「むやみな殺生をしない」というルールを教えるのもいいですね。
生物と無生物の違いを伝えるのもいいですね。
「かわいそうだから」と説明しても、ピンとこない子もいます。大人も害虫はためらいなく駆除しているのですから、子どもがそう感じるのも無理はありません。しかし、なかには機械を分解するのと同じように、虫を解体してしまう子もいます。そういう姿を見ると、親としてはやはり心配になるかもしれません。
そういう子には虫遊びを通して、生物と無生物の違いを伝えるのもいいと思います。虫を「虫さん」などと擬人化し、機械と比較しながら、ストーリー仕立てでお話をするなどの指導をしてみてはどうでしょうか。虫に対する好奇心を尊重しながら、生き物の生死については一線を引いて、しっかり説明していく。子どもはまだくわしくは理解できないかもしれませんが、幼いうちから倫理的なルールを学ぶ、いい経験になります。

篠山大明先生(信州大学医学部精神医学教室 准教授)
- 児童精神科医
ふだんは信州大学医学部附属病院子どものこころ診療部で診療をしています。子育て支援の発展を願い、日々の診療の傍ら、子どものストレスや発達障害に関する調査にも取り組んでいます。

信州大学医学部子どものこころの発達医学教室が開発した、「個性に合わせた多様な子育て」を応援するアプリ。周りの子と、自分の子を比べてしまって不安になる…。そんなときはこのアプリを開いて、子どものそれぞれの育ちについて学びましょう。AIチャット機能を新搭載!