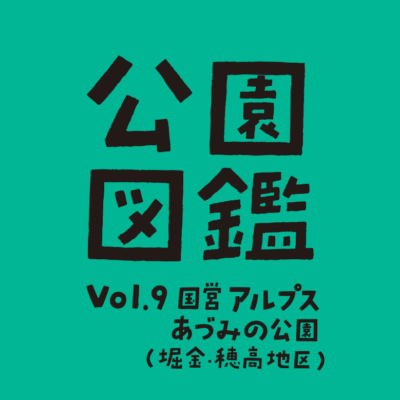【レポート】「TOCO-TON!わくわく!学校改革交流会」(主催:長野県教育委員会事務局 学びの改革支援課)

子どもたちが「好き」や「楽しい」、「なぜ」を追求するために、自分で学び方などを選択して、自己実現できる場所を目指し、“とことん”取り組む学校へ——。
そんな理想を形にしようと、長野県内の先生たちが動き出しています。
10月23日(木)、長野県総合教育センターで開かれた「TOCO-TON!わくわく!学校改革交流会」には、県内各地の学校・園の職員や教育委員会など教育活動に携わる方々が集結。「ウェルビーイング実践校 TOCO-TON(トコトン)」として活動する12市町村の発表や、大阪市立大空小学校の初代校長・木村泰子さんを迎えたパネルディスカッションが行われました。
子どもたちが主役の学校づくりを目指して、“とことん”取り組む長野県の取り組み。その最前線をレポートします。
● TOCO-TONの活動についてはこちらでチェック!
● 長野県教育委員会公式 Instagram
● 長野県教育委員会公式Facebook
■ 第一部レポート
子どもたちの「やりたい!」が動き出す――中信地域・松本市・安曇野市の実践校の活動報告より

交流会の第1部では、長野県内12市町村の「ウェルビーイング実践校TOCO-TON」が、それぞれの学校改革の取り組みを発表。ポスターやプレゼンを通じて、子どもたちが“とことん学ぶ”ための工夫や、現場で生まれた課題とその解決への道のりが紹介されました。
イクジィでは、読者のみなさんの多くが暮らす中信地域――松本市と安曇野市の実践校の取り組みをご紹介します。
■ “やりたい!”を“ともに”実現する学校を目指して 〜 松本市・安曇小中学校、大野川小中学校、奈川小中学校の挑戦
安曇小中学校・大野川小中学校・奈川小中学校の3校が合同で進めるプロジェクトでは、少人数校ならではの特性を生かし、学びを“まぜる×重ねる”試みが行われています。
小学1・2年生が行う3校合同の「乗り物遠足」では、子どもたちが自分たちで行き先を決めるところからスタート。先生が想定していたよりも時間がかかりましたが、焦らず見守ることで、子どもたち自身が納得して決めるまで考え抜く姿が見られました。
また、安曇小中学校が全校で学んだフィールドワーク「上高地学習」では、縦割り班でコースを企画し、当日も上級生が下級生をサポート。自然の中で互いに助け合い、異年齢で学び合う貴重な体験となりました。
先生たちはこう語ります。
「子どもたちの“やりたい”を形にするのは簡単ではありません。“やらせる”では意味がないし、“何も言わない”では進まない。子どもたちをどう後ろから支えるか、教師としてもそのバランスを探りながら学んでいます。」
■ 園から高校まで、地域でつながる“学びの連携” 〜 安曇野市・明北小学校、明南小学校、明科中学校の挑戦
安曇野市では、明北小学校・明南小学校・明科中学校の3校が中心となり、“園から高校まで一貫した地域の学び”を進めています。
たとえば、明科地域の園児・小学生・中学生・高校生が交流する活動では、年齢を超えて関わり合うことで、子どもたちに自然な“つながり”が生まれています。
園児の自然体験活動に小学校の先生が参加したり、園の職員が小学校を見学したりと、教員同士の学び合いも活発。小学校時代から中学校の先生や同じ地域の仲間と関わることで、進学時の不安が少なくなり、“顔なじみの安心感”が生まれているそうです。
■ 地域に根ざした教育を通じて、地域に愛される学校へ
子どもたちの「やりたい!」を起点に、先生たちが知恵を出し合い、地域ぐるみで学びを育てている松本市と安曇野市の実践校。少人数校や地域連携という特性を生かしたこれらの実践からは、子どもたちが互いに支え合い、自ら学びを広げていく姿が見えてきます。
子どもも先生も地域も“とことん”つながることで、新しい学校の姿が見えてきます。
■ 第二部レポート
「これからの学校の話をしよう」——子どもが主語になる学びへ

交流会の第二部では、「これからの学校の話をしよう」をテーマに、パネリストたちが現場のリアルな課題と希望を語り合いました。
登壇したのは、大阪市立大空小学校の初代校長・木村泰子さんと、県内のウェルビーイング実践校で改革を進める3名の先生方。コーディネーターを務めたのは、長野県教育委員会の武田育夫教育長です。
会場では、子どもたちを中心に据えた“新しい学校のかたち”について熱のこもった対話が交わされました。
■ “先生が主語の、子どもを育てる学校”から、“子どもが主語の、子どもが学ぶ学校”へ
木村さんは、「学びとは、子どもを変えることでも、校長が先生方を変えることでもない。大人が変わることです」と語り、「子どもが主語になるということは、大人が変わること。自分が変わるしかない」と強調しました。
その言葉に続き、武田教育長は“任せる”という言葉の中には「任・忍・認」の3つの意味があり、子どもに任せたあとは、大人が忍耐強く見守り、そしてその選択を認めることが大切だと話しました。
また、従来の通知表の“所見”をやめ、子ども自身が自分の頑張りや今後の課題を保護者に伝える“子どもが主導の懇談会”を導入した栄村・栄中学校の事例も紹介されました。
さらに、運動会の開閉会式を子どもたちに任せた、中野市・日野小学校の取り組みも紹介。子どもたちは6年生を中心に、自分たちで内容や演出を考え、大盛況の運動会をつくりあげたといいます。
どちらの事例も、大人が手を出さずに見守ることで、子どもたちは“自分たちでできた”という自信と誇りを実感していました。
“教えるプロ”から“学びのプロ”へ。実践校の先生方は、子どもを主語にした学びの実現に向け、試行錯誤を重ねながらも、日々の実践の中でその理想を少しずつ形にしようとしていることを語りました。
■ 誰もが当事者となり、“学校をつくる”
議論の最後に、木村さんは静かに、しかし力強くこう語りかけました。
「誰かにまかせたり、頼りきりになったり、うまくいかないことを人のせいにしてしまう――。
私たち大人がそんな姿を見せてしまうと、子どもも同じように“誰かのせい”にしてしまうかもしれません。学校から“人のせい文化”をなくすために、みんなが“学校をつくる当事者”になりましょう。
子どもは自分の学校を、保護者はわが子が学ぶ学校を、地域の人は地域の宝が育つ学校を、そして先生たちは自分の働く学校を――。助けが必要な子を支える力は、その子のまわりの仲間たちが育っていくことで生まれます。
一人ひとりが関わりながら、ときには失敗しても、支え合い、やり直せばいい。
みんなが当事者となってつくる学校が、子どもたちの命を守り、未来を支えていくのです。」
学校改革の中心にあるのは、子どもを信じ、任せ、支える大人の姿勢。
そんな“とことん”取り組む教職員たちの活動を通して、県内の学校現場では確かな変化が始まっています。
そして、この“学校づくり”は教職員たちだけのものではありません。
子ども・保護者・地域・教職員がそれぞれの立場から関わり合い、子どもたちの学びを支えること――
それこそが、長野県が目指す“ウェルビーイングな学校”の未来像です。
学校教育を「任せて安心」と思うのではなく、私たち保護者も“わが子の学びの環境を共につくる仲間”として関わっていくこと。
その小さな一歩が、子どもたちの安心と、未来をともに育てる力になっていくのかもしれません。